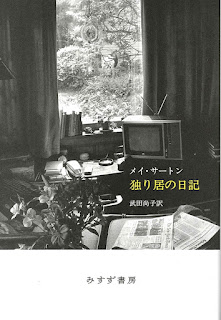回復のために、自分を「閉ざし」、居場所をつくる

私が回復するには、自分の中にいるあらゆる者たちに居場所をつくってやらなければならない。(中略)自分の中にいるさまざまな者たちが、互いに妥協することなく共存できる、その均衡点を私の体の奥深くに見つけなければならない。あらゆる者がもうここに来ているのだ。私の体はあらゆる者が集まる場所になっているのだ。だから、それらとともに新しくつくりかえなければならない。(p.95) 「熊になったわたし」 ナスターシャ・マルタン著 この本は、私の「今年の1冊」。 人類学者の著者は、フィールドワーク先のカムチャッカの森で熊に襲われ、九死に一生を得る大けがをします。 冒頭の引用は、事故の後、フランスに戻って治療を受けていたところです。 熊によって負った傷害を、単に外科的な回復としてだけではとらえられない、深い混沌に著者は陥っていきます。 この引用文は、まさにセラピーで起きること。 悩みや苦しみや困難を、心理療法という方法で扱っていくとき、そこには、そのクライエントさんには、(そしてセラピストの私にも)さまざまな「者」が現れてきます。 悩みや苦しみや困難の中にいるときというのは、たいてい、悩んだり苦しんだりしている者、それを何とかしたいともがいている者、諦めや無力感を感じている者、孤独を感じている者、それでも毎日を生きようとしている者… こんなふうにあらゆる「者」が現れて来ます。 そして、セラピーを通して、あらゆる者が「互いに妥協することなく共存できる、その均衡点」を探っていくのです。 私が変容するためには、肉体と魂の手術を完成させて、私という開かれた世界を閉じる必要がある。肉体の傷口を縫合し、開かれた魂を閉じるのだ。肉体においても、魂においても、今すぐ境界を閉鎖しなければならない。(p.96) 著者は大けがをしたので、損傷した肉体の傷を閉じ、肉体が回復していく必要があります。 心理療法でも、自分を「閉じ」、境界をつくるというのは、とても重要なこととして扱います。 心理療法では、いろいろな“実験”を通して「境界」を引く、「境界」を感じる、「閉じる/開く」、「つながる/切る」、「境界」を広げる/狭める、ということを体験していきます。 それは、自分の中に集まった「あらゆる者」にとって大切な感覚であり、「あらゆる者」とともに行います。 この本に関してもう1つ。 著者は、フランスで手術と治療を終えた...

.jpg)